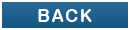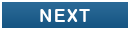|

ホーム >> 【個人のお客様への調査内容】 紛争事例
※「千葉県宅地建物取引業協会 研修会テキスト」 から抜粋したものです。
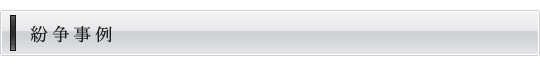 |
| |
 借地を誤信し誤って説明した 借地を誤信し誤って説明した |
売主の代理業者による誤った説明により、買主が借地権を誤信し締結した土地売買契約が、無効とされたケース
紛争内容
- 地主Aは、借地人Bに対して自己所有の土地を、木造の建物所有目的で期間20年と定めて賃貸した。
- 地主Aが死亡し、息子のCが賃貸人たる地位を承継した。
- 賃貸契約締結から20年経過した後、地主Cは借地人Bにこの底地を売却し、手付金を受領した。
- 宅地を売却した際、売主Cの代理として買主である借地人Bとの契約締結交渉にあたった代理業者Dは、借地権が存続するにもかかわらずBに借地権は消滅した旨を述べ、Bはその言葉を信用して、当該地を更地価格を基準とした価額で購入した。
- 売主Cが、買主Bに対して残代金の支払いを求めたところ、Bは、売買契約については、要素の錯誤があるので無効だと主張し、手付金の返還を求めた。
【買主(借地人)Bの言い分】
売買契約締結の交渉過程において、私は借地人が底地を購入するときは、通常、更地価格の3割位で購入できると主張していた。
ところが、地主Cの代理人として交渉に当った代理業者Dは、当該地の借地権は更新できるものであり、借地権は消滅していないにもかかわらず、私に対して、この土地の借地権は期間満了により消滅した旨を説明し、更地価格で購入するよう要求した。
専門業者の発言でもあり、これを信じて売買契約を締結した。
売買契約の重要な要素である売買金額の算出根拠について私の錯誤があったから、この契約は無効である。
【売主Cの言い分】
買主(借地人)Bは、代理業者Dが私の代理人と主張しているが、Dはこの売買に媒介業者として関与していたにすぎず、私の代理人ではない。したがって、Dの発言に私は責任を負わない。
Bが、当初、更地価格の3割位で底地を購入できるのではないかと言っていたのは事実だが、最終的にはDの説明に納得してその主張を撤回したではないか。
また、売買代金の決定には、Dが更地価格のうち借地権価格分30%を減額した金額を前提に説明・提案し、私とBの中間をとった金額でBも最終的には承諾した。
したがって、借地権の存在、借地権価格分の減額を前提として代金額が決定されたものであり、契約は有効である。
【本事案の問題点】
代理業者Dは、本来は借地権が存続するにもかかわらず、「借地権は消滅した」旨を誤って買主(借地人)Bに説明し、結局、更地価格にもとづく売買契約を締結さた。
【本事案の結末】
- 本事案では、売買契約の締結の際に、代理業者Dの誤った説明により、買主(借地人)Bの借地権が消滅したという前提で、更地価格を基準として代金額が決定されたことは明らかであった。
- 判決は、代理業者Dが代理人と同視できる立場で買主(借地人)Bと交渉したこと、本件売買の代金が更地価格と大差がないことを認定したうえで、Bが「借地権が消滅した」旨のDの説明を信じて購入価額を決定したのには、「要素の錯誤」があったとして、売買契約は無効であるとし売主Cに手付金の返還を命じた。
本事案に学ぶ
- 法定更新があれば借地権は存続する
本事案のケースでは、借地期間が満了しても法定更新されるため、当該地には借地権が存続する。
一定の法律関係を説明するときは、ときとして重大な結果をもたらす場合があるので細心の注意を払い、十分に調査検討すべきである。
また、借地借家法(旧借地法、旧借家法)等をよく理解しておく必要がある。
- 関係法律の誤った説明をすれば、業務責任を追及される
本事案の裁判の中では、直接問題とはなっていないが、買主(借地人)Bについては、代理業者Dに対する損害賠償請求が可能となり得た。
Dが真実とは異なる説明を故意にした場合はもちろん、仮に過失により旧借地法にもとづく法定更新を誤解して説明したのであればあまりにも初歩的な法律知識であるために、不動産取引の専門業者として、業務責任を追及されても仕方のないケースである。
- 借地等の権利関係については、事実関係の確認を行う
■借地等の権利関係の調査上のポイント
●事実関係の確認を行う
・借地契約書の特約等、内容のチェック
・当事者から直接内容を開き、書類として整理したうえ事実関係を確認する
●不明な点は、弁護士等の専門家に相談する
法律関係について、不明な点があるときは、事実関係等を整理した関係書類を持参し、弁護士等の専門家に相談する。
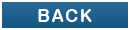 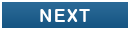 |
|
|
|
COPYRIGHT(C)2008 宅地開発設計 有限会社アットプレイン ALL RIGHTS RESERVED.
|
|

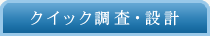
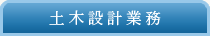
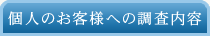
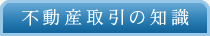
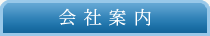

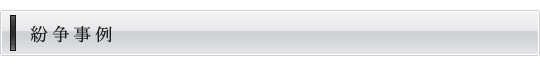
 借地を誤信し誤って説明した
借地を誤信し誤って説明した